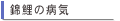今から約200年前、新潟の山古志村およびその周辺地で養殖していた食用鯉が突然変異を起こし、稀に赤や黄色などの鯉がうまれるのを見た一部の者が積極的に色鯉の品種改良に取り組み始めたといわれています。これが錦鯉の歴史の起源で、明治時代には「世の中に美しき鯉あり」という言葉が人々の間に伝わるようになり、紅白などの品種改良が行われました。(元号一覧はこちら)  大正3年(1914年)に開かれた大正博覧会によって、錦鯉が次第に広く社会一般に知られるようになってきました。大正時代に作出、固定された品種には、大正三色、黄写り、白写り、浅黄などがあり、昭和になると、昭和三色、金団扇、銀団扇、金兜などが固定され、昭和7年(1932年)には新潟県水産試験場が阿賀野川養魚場を設立し、本格的に錦鯉の改良研究を始めました。 大正3年(1914年)に開かれた大正博覧会によって、錦鯉が次第に広く社会一般に知られるようになってきました。大正時代に作出、固定された品種には、大正三色、黄写り、白写り、浅黄などがあり、昭和になると、昭和三色、金団扇、銀団扇、金兜などが固定され、昭和7年(1932年)には新潟県水産試験場が阿賀野川養魚場を設立し、本格的に錦鯉の改良研究を始めました。戦後、品種改良は一時停滞したものの、ネズ黄金が固定されて以来、様々な「光もの」が作出されるなど、錦鯉の黄金時代を迎えることになりました。ドイツ鯉と錦鯉を交配させて、秋翠をはじめ、名前に「ドイツ」を含むドイツ系各種を作り出したことや、青木沢太氏親子が2代25年間に渡って苦闘して作り上げた黄金種は、今日の錦鯉作りに大きな役割を果たしたといえます。 錦鯉の品種は、固定品種とバリエーションを含めると、今では80種にも及ぶと言われています。INPCでは26種類を固定品種に指定し、それ以外のかけ合わせによる品種をバリエーションとして捉えます。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||